疲れきってしまわないようにすることだね。そうでないと、車輪のしたじきになるからね。
ヘルマン・ヘッセ
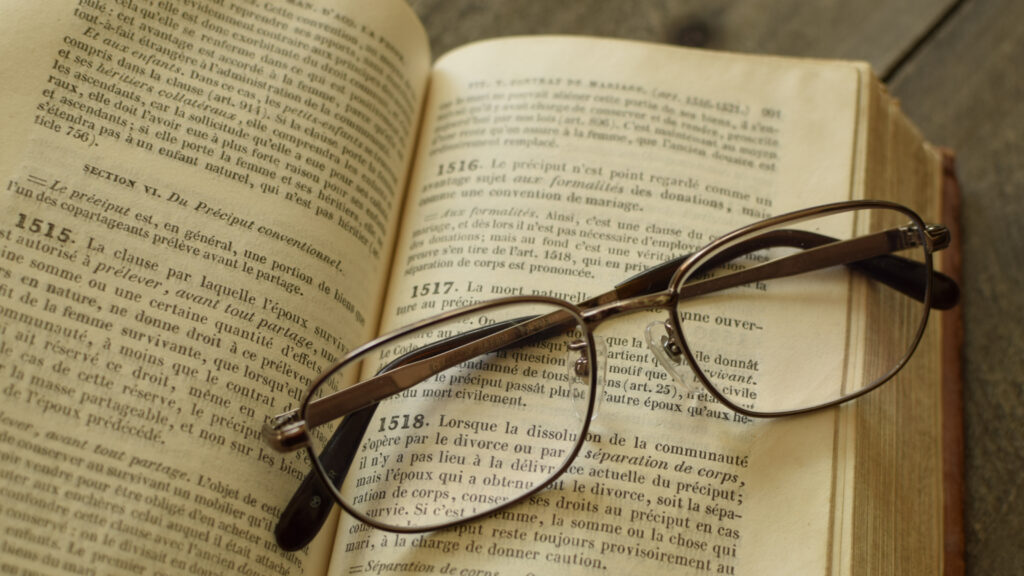
今日の「ことば」について
ドイツの作家ヘルマン・ヘッセ(1877-1962)は、20世紀を代表する文学者の一人であり、特に若者の内面や成長を鋭く描いた作品で知られています。
代表作の一つ『車輪の下』(1906年)は、才能ある少年が厳しい教育制度や周囲の期待に押しつぶされていく姿を描いた小説です。
本作の中で語られる「疲れきってしまわないようにすることだね。そうでないと、車輪のしたじきになるからね。」という「ことば」は、当時の過酷な教育制度に対する警鐘であると同時に、人が生きていく上での普遍的なメッセージを含んでいます。
表面的には「過度に自分を追い込みすぎると、社会や制度といった大きな仕組みに押しつぶされてしまう」という意味であり、心身のバランスを崩さないことの大切さを説いています。時代背景としては、産業化が進み、効率や成果が強く求められる中で、人間性を損なうことへの批判が込められています。
社会保険労務士としての解釈
社会保険労務士としてこの「ことば」を考えたとき、「疲弊を避けることの重要性」は、まさに現代の労働環境にも深く通じると思いました。
まず事業主の視点から見れば、社員が疲れ果ててしまう状況は、労務リスクの高まりを意味します。
過労による健康障害やメンタル不調、ひいては労災認定や離職増加といった事態は、組織全体の生産性低下につながります。
故に、人材マネジメントの観点からは、「適度な休息」と「持続可能な働き方」を組織設計に組み込むことが不可欠でしょう。
働き方改革関連法に基づく時間外労働の上限規制や、年次有給休暇の取得義務化なども、この「疲れきらせない」仕組みづくりの一環と捉えることができます。
一方、労働者の視点では、自らのキャリア形成や健康管理において「限界を見極める力」が必要だと思います。
成果を求めて無理を重ね過ぎれば、心身を壊し、長期的なキャリアに傷を残しかねません。
仕事と生活のバランスを意識し、休むことを「弱さ」ではなく「持続のための戦略」と捉える、マインドチェンジが求められます。
また、権利意識としても、労働基準法で保障された休憩・休日・有給休暇の取得は当然の権利であり、それを活用することが「車輪に押しつぶされない」ための手段といえるでしょう。

社会保険労務士としての具体的アドバイスは、制度と現場をつなぐことです。
例えば、労働時間の適正な管理を支援し、長時間労働が常態化しない仕組みを導入すること。さらに、ストレスチェック制度を活かして職場のメンタルヘルスを予防的に支えること。
こうした制度的支援を通じて、「疲れきらない」働き方を実現することが、私たちの専門的役割だといえます。
今日の「ことば」から学ぶ現場のヒント
この言葉を現場で生かすためには、日常の小さな配慮と実践が大切です。
事業主にとっては、まず「休みやすい雰囲気づくり」が重要でしょう。有給休暇の取得を数字だけで管理するのではなく、上司自身が率先して休暇を取り、休むことを推奨する文化を築くことが効果的です。また、繁忙期には業務分担を調整し、誰か一人に過重な負担が集中しないようにする体制も欠かせません。
従業員にとっては、日々の自己管理が鍵となります。睡眠、食事、適度な運動といった基本的な健康習慣を整えることはもちろん、仕事を抱え込みすぎないために上司や同僚に相談する勇気も必要です。さらに、キャリアの中で「力を抜く時期」を持つことは、むしろ長期的な成長につながります。
制度と文化の両輪を整え、働く人が「疲れきる前に休む」ことが自然にできる環境を育むことが、車輪のしたじきにならないための現場の知恵といえるでしょう。

結語
ヘッセの言葉は、単なる若者への忠告ではなく、現代社会で働くすべての人への普遍的な警鐘です。人は制度や組織の中で生きる以上、「疲れきらない工夫」を持たなければ、知らず知らずのうちに押しつぶされてしまいます。

事業主も労働者も、「持続可能な働き方」を意識し、制度と実践を両立させていくことが大切なのではないでしょうか。
社会保険労務士としての役割は、その橋渡しを担うことにあります。
この言葉を胸に、日々の働き方を見直すきっかけにしていただければ幸いです。
ヘッセの言葉は、単なる若者への忠告ではなく、現代社会で働くすべての人への普遍的な警鐘です。人は制度や組織の中で生きる以上、「疲れきらない工夫」を持たなければ、知らず知らずのうちに押しつぶされてしまいます。
事業主も労働者も、「持続可能な働き方」を意識し、制度と実践を両立させていくことが大切なのではないでしょうか。社会保険労務士としての役割は、その橋渡しを担うことにあります。この言葉を胸に、日々の働き方を見直すきっかけにしていただければ幸いです。

お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください

